 
   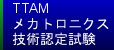   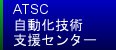 
「大学はでたけれど」を思う
国立長野高専教授・副校長 山崎 保範(自動化推進協会常任理事)
アラ還世代の我々の多くは、親などの先人が口にした、「大学は出たけれど」を聞いたことがあるだろう。昭和4年、小津安二郎監督の同名の映画であり、流行語になったとのことである。戦後の日本でも、“ドルショック”、“オイルショック”、“バブル崩壊”などの不況があり、その度にこの言葉が囁かれていた。が、我々理工系の学生にとってはそれ程深刻な状態にはならず、希望者全員無事就職できたようである。
ただ、今回の“リーマンショック”から“ギリシャの信用不安/ユーロ危機”による不況はどうも様子が違うように思える。
それは“もの本位制”から離れて、現実の“もの”との兌換性のない、“証券”とか“信用”といった、謂わばバーチャルな世界からのしっぺ返しとしか思えない。これは、“ものづくり”に生きてきた我々エンジニアにとっては憂慮すべき事態である。今までも100円ショップに行く度に「これを100円で買えることは、消費者の僕にとっては嬉しいことだが、作り手としての私から見ると悲しいことだ」と思っていた。これも、もの自体の個々の価値を無視した値付けという意味で、もの離れの走りである。しかし、ここではそのシステムの良否を問うことはしない。何せ、「英国で起きたことは米国で、米国で起きたことは日本で起きる」と謂われているように、約250年前に起きた産業革命に始まるヨ−ロッパの考え方・手法を必死で学び、追ってきて“先進国”になったのが、他ならぬ日本だから。
そして、戦後一貫してそれを支えてきているのが、我々エンジニアであることは間違いない。しかし、こと“ものづくり”に限定すると、その地位は揺らいでいる。第二次産業の就業者割合が、30%を切って久しいし、第三次産業のそれの半分にも満たない。既に、“産業の空洞化”という言葉すら陳腐化し、海外生産が中小企業においてもあたり前となっている。ある中小企業では、国内60人、中国1200人である。
当面の企業の利益・存続を考えると、海外生産を考えざるを得ないだろう。日本で研究開発し、海外で100%生産という図式を是とせざるを得ないかも知れない。しかし、エンジニアという立場を離れても、これは長期的に見ると製造メーカを、ひいては日本の国力を落とすことは間違いない。先述の通り、一番先に変化したのは英国で、シティを舞台にしたマネーゲームもここから始まり、現代の英国工業力は衰退している。その結果、総じて言えばハッピーな状態にあるとは思えない。 この悪しき前例の轍を日本が踏む必要はない。どう考えても、日本人は“ベニスの商人”にはなれそうもない。逆に、少なくとも江戸後期の日本人はものづくりが大好きな民族であった。1976年には、細川半蔵の著書『機巧図彙』が出版されているのが、その証拠である。一般庶民にまでものづくりが浸透していたに違いない。その血が、ものづくり大国・ロボット大国を支えてきたのではないだろうか。
目の前の物が動き出す感動、目に見えないような微小部品が1秒タクトで組みてられる驚き。目の届く範囲に現場があり、場合によっては設計者自らねじ締めもできる。この環境なくしては、日本の研究開発も衰退するに違いない。日本から現場を奪った高労務費・円高は自動化技術者の復権により克服したい。幸い、心ある企業はこれに気づいているし、高専・大学などでも、手も動かす教育が始まっている。これにより、大卒を嘆かない時代の再来を期したい。
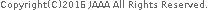
|